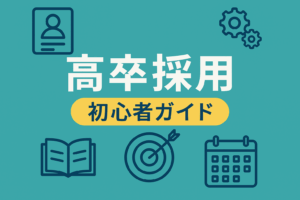組織のヨコのつながりをどのようにして強めていくか
こんな悩みありませんか?
「部署内では協力し合えているのに、他部署との関わりが薄く、連携がうまくいかない…」
このような悩みは、業種・規模を問わず多くの企業で共通するものです。
結果として、情報共有の遅れや業務の重複、部分最適による非効率が発生してしまいます。
なぜヨコのつながりが希薄になるのか?
- 役割の専門化と縦割り構造の定着:部署ごとの目標に集中することで、他部署の意図や事情が見えづらくなる
- 異動や交流の少なさによる「他人事化」:他部署との接点が限られ、連携する意義や目的が曖昧なままになる
- 評価制度が「個別の成果」に偏っている:ヨコの連携をとることが自部署の評価に直結しないため、動機づけが弱い
➡1つの会社に属する仲間であるはずなのに、小さな会社の集合体のような状態になってしまっている。
会社全体の問題であるはずなのに他人事、組織間の業務に一塩足りない(配慮が足りない)、情報共有しない、議論しない(会社にメリットの無いケンカばかりおこる)
ヨコのつながりを強める3つのアプローチ
① チームビルディング研修の実施
部署を越えて同じゴールに向かう体験を通じて、一体感と信頼関係を構築。
特に管理職層を対象に非日常の空間(県外や離島の会議室がある旅館・ホテル等)で実施することで、役職や壁を越えた対話が生まれやすくなります。
中小企業でも活用しやすく、成果が出やすいアプローチです。
② ジョブローテーション・横断プロジェクトの推進
異なる部署間で仕事を経験させることで、他部署の視点と事情を理解しやすくなります。
部署単位ではなく「会社単位の最適化」の意識が育ちます。
ただし、中小企業ではジョブローテするほどの人材が揃ってなかったり、制度として確立していない場合が多いので、横断プロジェクトがおすすめです。
横断プロジェクトの例としては、HPリニューアルを若手中心にプロジェクト化したり、SWOT分析をプロジェクト化して各部署から募って実施することが挙げられます。注意点としては、プロジェクトを推進するリーダーの力量で成果が変わってくるので、経営層からの十分なサポートが必要であるということです。
③ 制度設計の見直し
ヨコの連携が評価に反映されるような体制づくり。
単なる成果主義から「協働・貢献」を重視する文化へシフトすることが求められます。
こちらに関しては、非常に有効な手段ではありますが、制度設計に時間がかかる(半年~1年)ことがデメリットです。
まとめ
- ヨコのつながりの希薄化は「仕組み」と「意識」の両面で解決が必要
- 自部署の成果だけでなく、会社全体の最適化を見据えた取り組みが重要
- チームビルディング研修は、連携の起点づくりとして特に効果的
ご相談はこちら
「部署間連携」や「組織の一体感」に課題を感じている経営者・人事担当の方へ。
中小企業診断士として、貴社に合わせた施策のご提案・実行支援をいたします。
お気軽にご相談ください。
▶︎ お問い合わせフォームへ